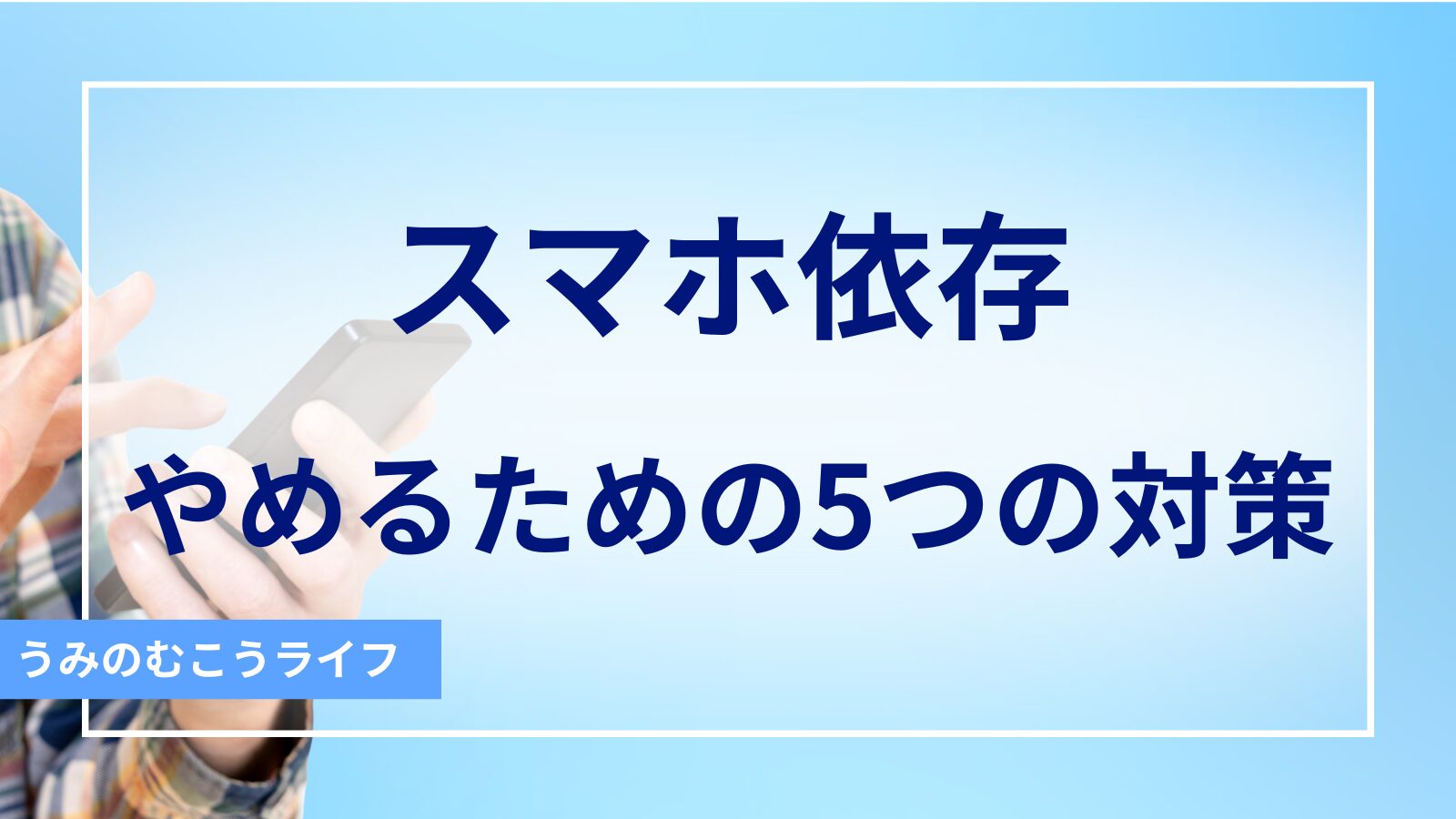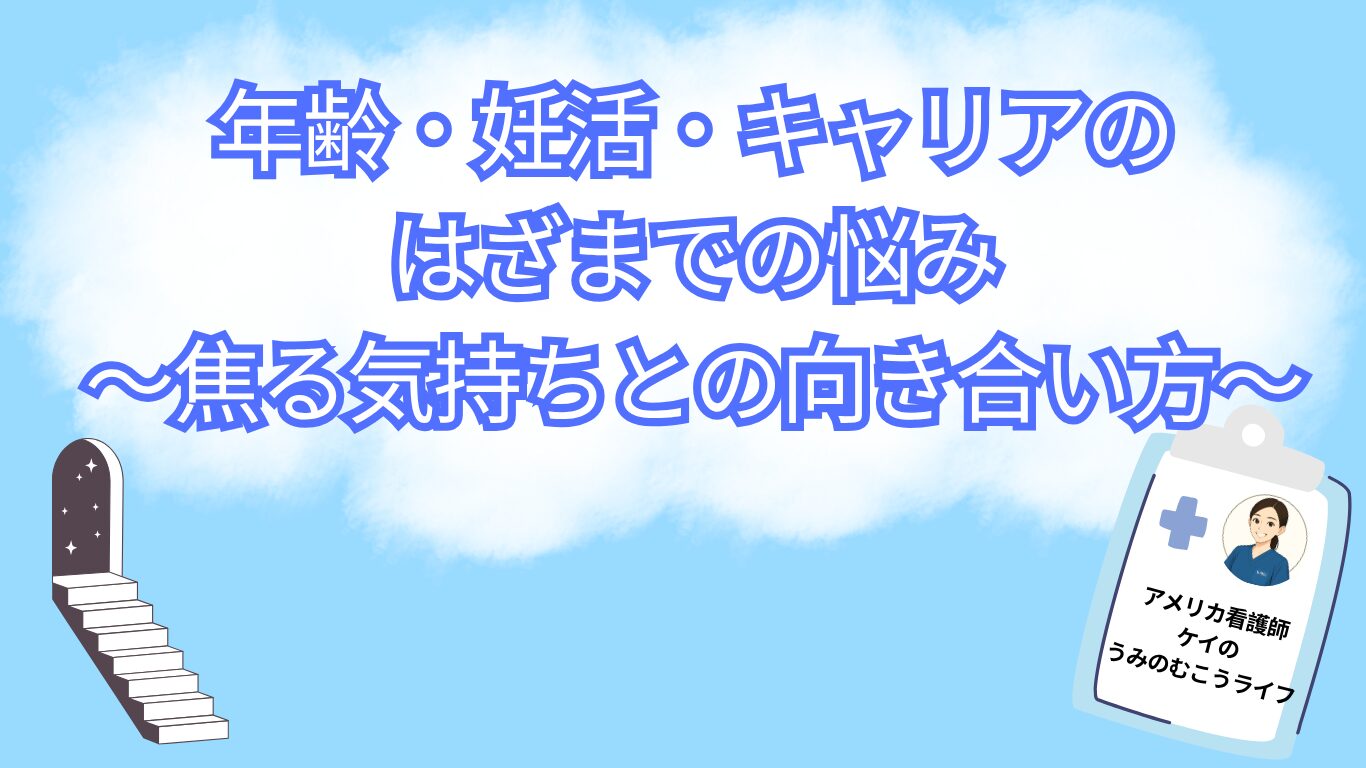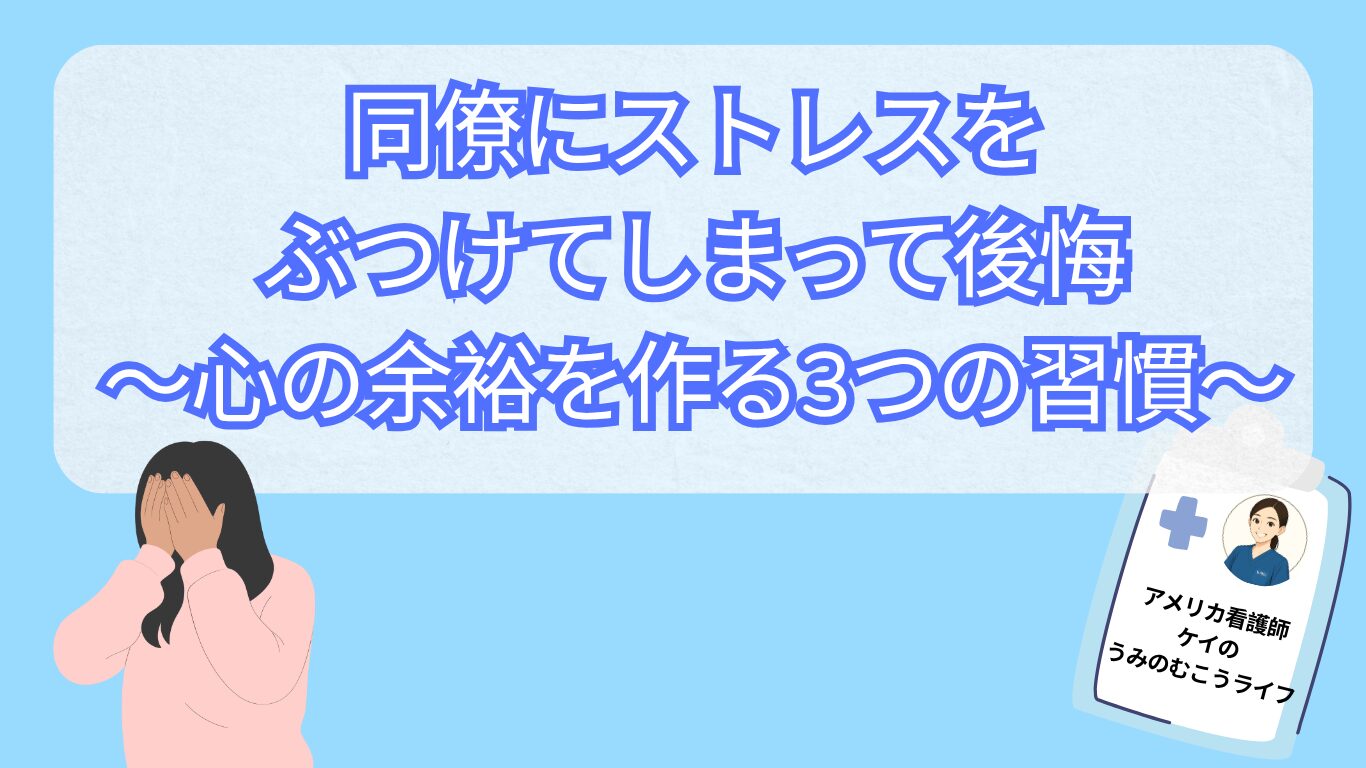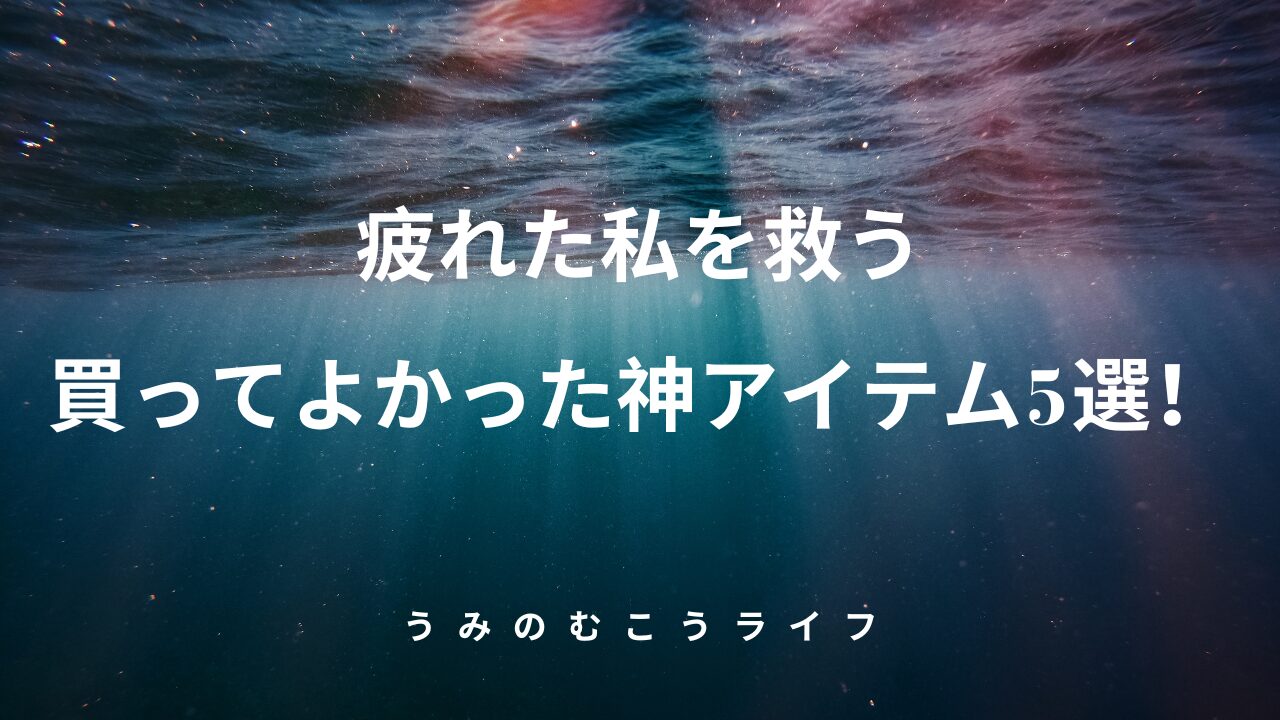試験後のバーンアウト(燃え尽き症候群)│気づけず沈んだ私が抜け出した話
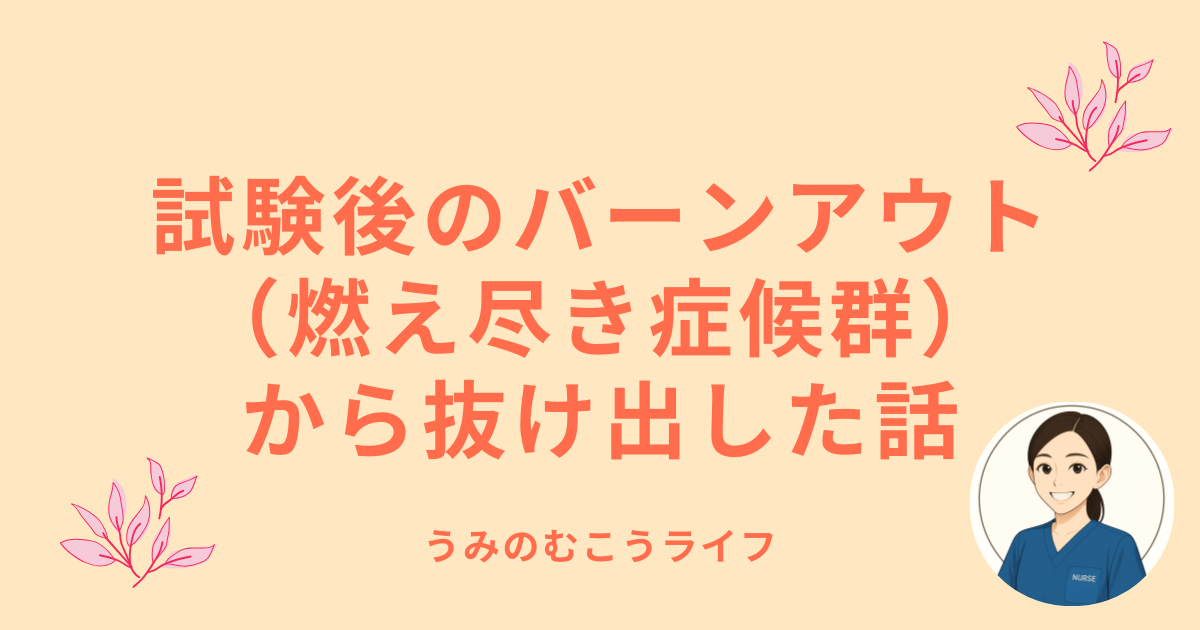
みなさん、こんにちは!
アメリカ看護師のケイです。
今回は、看護師試験のあとに体験した、燃え尽き症候群についてのお話になります。
正直、私は自分がバーンアウトしていることに気づけませんでした。
気持ちが落ちきって、何をしても元気が戻らない―――それが一番怖かったです。
私にいったい何が起きているのか理由もわからないまま沈む感じ。
自分では解決できない。人にも話すのが怖い。
藁にもすがる思いで心理カウンセリングに行き、「なぜこうなっているかわからない」と伝えたところ、「試験後なら燃え尽き症候群かもしれませんね」と一言。
すとんと腑に落ちました。
1時間のカウンセリング。最初の15分でその言葉を聞きました。
正直、その後に何を話したのかはほとんど覚えていないくらい、ほっとしたのを今でも覚えています。
でも、名前が付いたところで「で、何をすれば治るの?」は別問題。
私は『精神科医が教えるストレスフリー超大全』に書かれていた”不安や悩みの対処法”を、無理なく続けられる範囲で忠実に実行しました。
結果として、1~2か月で心が晴れて、「元に戻った…むしろ前より元気な気がする」と言えるところまで回復しました。
この記事では、同じように迷っている方の小さな手がかりになればと、バーンアウトに気づけなかった私が抜け出すまでの道のりについてお話します。
「気づくこと」と「整えること」
私に必要だったのは、元気になるための気合ではなく方向づけでした。
その時の状態に「燃え尽き」という名前が付いた瞬間、やることがシンプルになりました。
まず、睡眠と体内時計を整える。
次に、食の選び方を少しだけ変える。
そして、小さな達成を言葉にする。
派手さはありませんが、これを行うことで静かに回復が進みました。
気づけなかった理由――走り続けたあとの空白
試験に向けて走っている間は、アドレナリンがずっと背中を押しています。
ゴールを越えたあとにその支えが急に消えると、体と心が同時に抜け殻のようになることがあります。
私はそれを“ただの疲れ”だと思い込みました。
休めば戻るだろう、と。
ところが数日たっても気分が上がらず、朝の支度が遅くなり、好きなことに手が伸びない。
理由がわからないまま沈んでいく感覚がさらに不安を増やし、気づくのが遅れていきました。
カウンセリングで名前が付いた瞬間
カウンセリングでは、ここ最近の状況を話しただけで、先生が「燃え尽き症候群かもしれませんね」と静かに言ってくれました。
その瞬間、絡まっていた糸がほどけるようにすっきりしました。
”原因がわかるだけで人は少し楽になる”ということ、をまさに体感しました。
しかし、気づき=回復ではありません。
けれど、回復の入り口には間違いなく立てました。
人に話すことの大切さ
もう一つの気づきは、一人で抱え込まないことです。
燃え尽き症候群だとわかる前は、今の自分の状態を人に話すのが怖くて、誰にも言えませんでした。
けれど、ラベルが付いたあと、勇気を出して「実は最近気分がすぐれなかった」と友人に話してみたところ、即座に「それって、燃え尽き症候群じゃない?」と返ってきました。
答えは、案外すぐそばの人が知っているのだと、改めて感じました。
たとえ詳しく話さなくとも、短く状況を伝えるだけで、視点が増えて気持ちが楽になるかもしれません。
回復に向けての4つの方法
1, 朝の散歩:体内時計を整える
朝起きてから30分以内に外へ出て、10~20分ほど歩きました。スピードは気にせず、まず光を浴びることを優先しました。
雨の日や予定通りに起きられなかったとき、窓辺で朝ご飯を食べるだけの日もありました。
前夜に、朝着るものを準備しておくと、散歩に行こうかという迷いが減りました。
数日すると、寝つきと目覚めた時の気分の重さが少しずつ軽くなっていきました。
2, 食の置き換え:完ぺきではなく、継続できるように
理想は「健康的な食事に総入れ替え」です。でも、それは続きません。
私は置き換えだけにしました。
お肉の代わりに魚、魚の気分ではない日はお豆腐や豆類。
サラダ油の代わりにオリーブオイル。
白米の代わりに玄米や全粒粉パン。
私の場合、玄米だけだと美味しいと感じることができなかったので半半米(バンバンミー)という、もち米と玄米が半々で入っているものを購入していました。
また、買い物ではメニューに関係なく「魚か豆類のどちらかは必ず買う」ということを決めているだけで、置き換えの選択が安定しました。
もちろん、お肉を食べる日もあるし、白米を食べる日もあります。
できる日の少し良い選択で十分です。継続することが大切です。
3, 3つのポジティブ:できたことを、声に出す
1日の終わりに、”今日のよかったことを3つ”声に出して言いました。
本には3行日記とありましたが、書くことが億劫になり継続できなくなることよりも、自分が継続しやすい方法で取り組もうと思い、声に出すことにしました。
大きな出来事でなくて大丈夫です。
「笑顔で挨拶ができた」
「夜ご飯を自分で作れた」
「電車で席を譲った」 など。
やりだした頃は、たった3つの良いことが中々出てきませんでした。
けれど、口にするのを続けていくと、生活している中で「あっ、この良いことは今日の夜言える」と小さな良いことに気づけるようになっていきました。
こうして注意の向きを少しずつ、ポジティブなことに向けていきました。
4, 運動後の一言:「すっきりした」と言語化する
運動は散歩やストレッチなど、着換えずにできる軽さから始めました。
運動が終わったら、必ず「はぁ~、すっきりした」と口にします。
しんどかった感覚より、終わった後の爽快感を自分に聴かせるためです。
これを続けると「また少し歩こう」という気持ちが自然にわいてきました。
まとめ
再出発するには、小さなことの積み重ねでした。
- 自分がどんな状態であるか気づくこと。
- 体のリズムを整えること。
- 無理なく、続けられる形で淡々と。
- 一人で抱え込まず、信頼できる人に話す。
最初の2週間は、正直大きな変化はありませんでした。
3週目あたりで、少し心に余裕が持ててきたという感覚になりました。それでも、仕事中はいつもよりピリピリ・イライラしていたと、後ほど同僚から聞きました。
回復は思ったようにスムーズにはいかないけれど、完璧である必要もありません。
うまくいかない日は、一度止まって休みましょう。
また明日から、ゆっくり前に進みましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
※急な悪化や日常生活に強い支障がある場合は、無理をせず医療機関や専門家に早めに相談してください。